



株式会社日本電力サービス(東京都多摩市)
現業開発本部 技術管理部長
※内容は2021年3月時点のものです
住宅の屋根に太陽光発電設備を設置しているお客さまからの依頼が中心です。背景には、太陽光を含む再生可能エネルギーで発電した電気を、決められた期間・価格で電気事業者が買い取ることを義務付ける制度があるのですが、2019年から買取期間が順次終了を迎えています。売電単価の低下を受けて、昼間発生した太陽光の余剰電力を蓄電池にためて自家消費した方が、メリットが大きくなっています。また、台風や地震といった自然災害の増加により、蓄電池を停電時の非常用電源として活用したいというニーズも高まってきていると思います。

工事を受注した後、お客さま宅を訪問し、事前の現地調査を行います。その後、設計を行い、工程調整、材料の手配、施工といった流れになります。施工日は蓄電池本体をコンクリート基礎に据え付けるとともに、パワーコンディショナー(直流・交流変換装置)の取り付け、蓄電池からパワーコンディショナー、分電盤までの配線作業、機器の動作確認などを行います。蓄電池は容量4.2kWhから8.4kWhまでの製品を取り扱っています。戸建てがほとんどですが、集合住宅での施工実績もあります。

事前調査では、お客さまが希望する蓄電池の設置場所に十分なスペースがあるか、設置基準を満たしているかを確認します。蓄電池から分電盤までの配線ルートにもあたりをつけます。調査がしっかりできていないと、設計や施工などの後工程に影響しますので、とても重視しています。
新たにケーブルを通すため、建物によっては壁の穴あけなども必要となりますが、できる限り仕上がりがきれいになるように注意しています。蓄電池は一般の方にはなかなかイメージしにくいシステムです。お客さまには蓄電池の概要とともに、工期や完成後の状態を工事着工前に具体的かつ丁寧にお伝えし、ご理解いただけるように心がけています。

工場で建築物や一部の部材を製造し、現場で組み立てるプレハブ工法で建てた住宅は、ケーブルを通すための通線の位置がハウスメーカーでなければわからないことが多く、工務店を通じて問い合わせをしなければなりません。
また、最近の住宅は断熱構造になっており、壁の厚さが300~400mmもあるので、穴あけは難しく、どのように通線するか工夫が必要となります。お客さまがお住まいの既設住宅が主な対象ですので、新築に比べ工期は限られています。先ほどもお話ししましたように、事前の調査・準備で課題を解決しておくことが大切だと認識しています。
私自身は管理責任者という立場ですが、現場で作業をする機会も多いです。蓄電池に限らず、ビルや工場などの規模の大きな高圧受電設備の工事なども担当しており、幅広く現場を経験させていただいています。日々様々な工事案件に携わっていることもあり、全ての案件について、予定通り完了したときには達成感があります。しかし、この仕事を本当に熟知するには20年、30年は必要だと思います。私はまだ10年ほどですが、やり切ったという現場、満足した現場はまだまだありません。
以前は鋼製建具・ガラス販売代理店に勤務し、そこで15年間働きました。そのときに、現場で電気工事代理人の仕事ぶりを見ていて、難しそうな仕事だという印象があり、興味を持ちました。新しく電気工事の仕事にチャレンジしたいという思いから転職を決意し、現在の会社に入社しました。
同じ建設分野で働いていましたが、職種が違いますから、電気工事士の資格は持っておらず、入社してから試験勉強を始めました。一気に第一種の資格取得を目指し、仕事が終わってほぼ終電で帰宅した後、午前2時ぐらいまで筆記や技能の試験対策に時間を費やしました。あのときは本当にきつかったですね。約1カ月間にわたり集中して取り組み、苦労のかいもあって、1回目の挑戦で合格することができました。
図面を書く際の基礎になっていると思います。試験に出てくる複線図作図問題や記号問題は今でも参考になっており、当時の参考書を繰り返し見直しながら、配管や配線、器具の配置などの作図作業に役立っています。
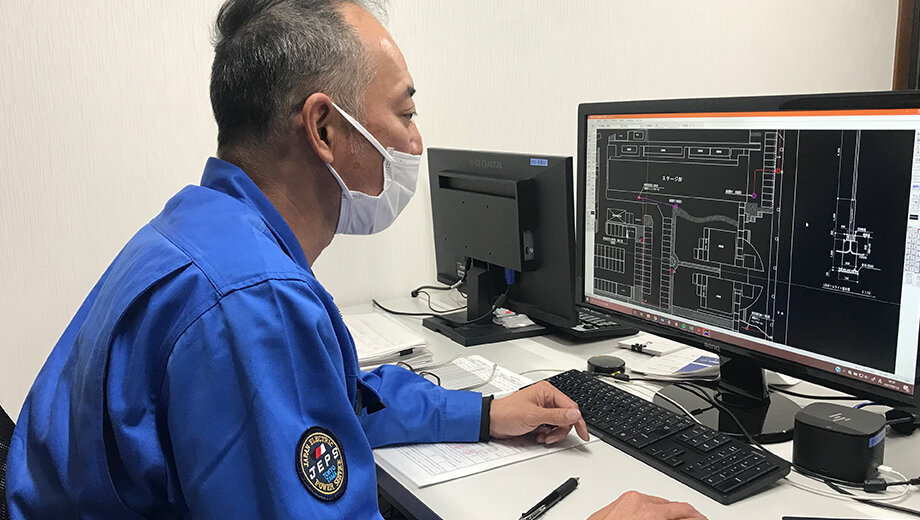
ただ単純に資格は仕事をするために必要という考え方ではなく、希望する職種の勉強が効率的にできる貴重な機会だと思っています。資格取得のその先を見据え、自分が将来、電気工事の仕事に就くこともイメージしながら取り組むとやる気も上がるのではないでしょうか。
資格の勉強をしていれば知識が身に付きますし、それに現場の経験が加われば「強い電気技術者」になれると思います。この仕事は一つとして同じ工事はなく、常に新鮮な緊張感があり、慣れるということがありません。奥の深さが電気工事の尽きない魅力だと実感しています。今後、電気工事業界を目指す人が増えることを願っています。