



株式会社ソウワ・ディライト
工事部(群馬県前橋市)
※内容は2020年1月時点のものです
私はハノイ近郊の出身で、ハノイ電気大学に入って3年間電気について学びました。ベトナムでは電気技術者は高い知識を持った人としていいイメージを持たれており、社会的ステータスも高いです。国内で電力システムの普及や高度化が進んでいて、これからさらに発展していくのに貢献したいという思いもありました。
また、技術が進んでいる日本で勉強したいと考え、大学卒業後に日本語学校にも1年間通いました。その間に今の会社の社長がベトナムに来て、日本で働く電気工事技術者のリクルートをしていることを知り、面接を受けて合格することができました。その後、2018年の9月に日本に来て今の会社に入社しました。

道路がきれいなことや、バイクが少なくて車がいっぱい走っていることに驚きました。日本の食事は全然大丈夫でしたが、納豆だけはダメですね。また、最初は電車の乗り方や生活費の支払い方などがわからなくて戸惑いました。
来るまでは人間関係などが少し不安でしたが、日常のことも仕事のことも、みんな優しく教えてくれてよかったです。

最初はしばらく社内で勉強をしました。日本語のあいさつや日常会話に始まり、電気工事の専門用語なども学びました。現場に出る前にこうしてしっかり勉強する期間をとってもらえるなど、当社は外国人社員へのサポートも充実していてありがたいです。
現場に出られるようになってからは、先輩の指示に従って、電気工事士の資格がなくてもできる範囲の補助作業をしました。指示はもちろん日本語で、勉強したとはいえ現場の言葉は独特ですから、理解できるようになるまで大変でした。
ベトナムでの現場経験は大学卒業前に約3カ月実習に出ただけなので、ベトナムの電気工事にあまり詳しいわけではありませんが、現場作業に対する考え方や進め方は両国でかなり違うと感じます。特に日本では安全が一番大事だと考えられていて、そのためにルールや正しい作業の順序を必ず守らなければなりません。それが日本の良いところだと思いますし、きっちり手順などが決まっている方が私としてはやりやすいです。
それと、電気工事士の国家資格が必要なことは日本に来て知りました。ベトナムでは資格試験はなく、条件を満たした大学を卒業することで免許がもらえ、現場を経験して仕事を覚えるという制度になっています。
現場で本格的な仕事ができるようになりたかったので挑戦することにしましたが、電気の勉強と日本語の勉強を両方やらなければいけなくて大変でした。電気についてはベトナムで学んだことと共通する内容もありますが、それも日本語がわかっていなければ試験では解答できません。3月頃から勉強を始め、6月の筆記試験に臨んだときには1回目で合格できるとは思っていませんでした。実技試験は会社で練習することができたので、筆記試験ほど難しくは感じませんでした。
色々な人に教えてもらったことで合格でき、とてもうれしかったです。周りの人もすごく喜んでくれました。

免状を得たことで現場に行くチャンスが増え、様々な工具に触れることも多くなりました。現場の工具などを日本語で何と言うか覚えるのは難しいですが、試験勉強で名前や使い方を覚え、現場で触れてだんだんスムーズに扱えるようになってきました。図面の見方なども少しずつわかってきました。
まだ免状を得てから間もないのでそれほど大きく仕事内容は変わっていませんが、これからやれることがもっと増えると思います。配線や電線の接続方法は、基礎的なものだけでなくいろいろなやり方をできるようになりたいですし、照明器具やコンセントなどの設置についても、指示を聞くだけでなく自分で判断ができるようになっていきたいです。
第二種電気工事士試験を受験する留学生たちに、自分の経験を踏まえて勉強方法や電気工事の仕事についてアドバイスしました。たくさんの後輩が合格をめざして挑戦するのはうれしいですし、応援したいです。外国人で国家資格に合格するなんて無理だと思うかもしれませんが、最大の壁である日本語をしっかり勉強すれば合格は可能だと伝えました。
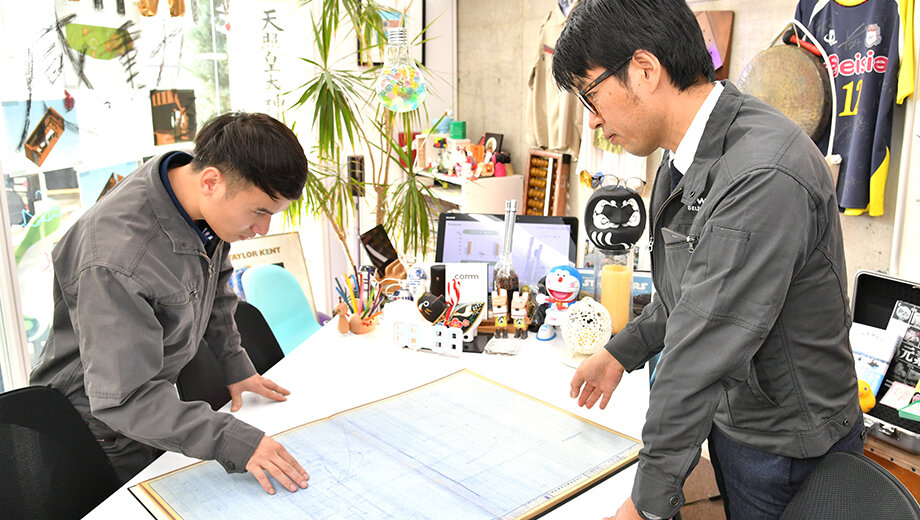
もっと現場で働いて、できれば日本で長く仕事をして、技術を高めながら日本人のやり方、考え方を学びたいです。そのために、日本語能力試験でより上のレベルに合格したり、自動車の運転免許を取得したりできればと考えています。また、いずれベトナムに帰るときには、日本で学んだことを生かして国の発展の役に立ちたいです。